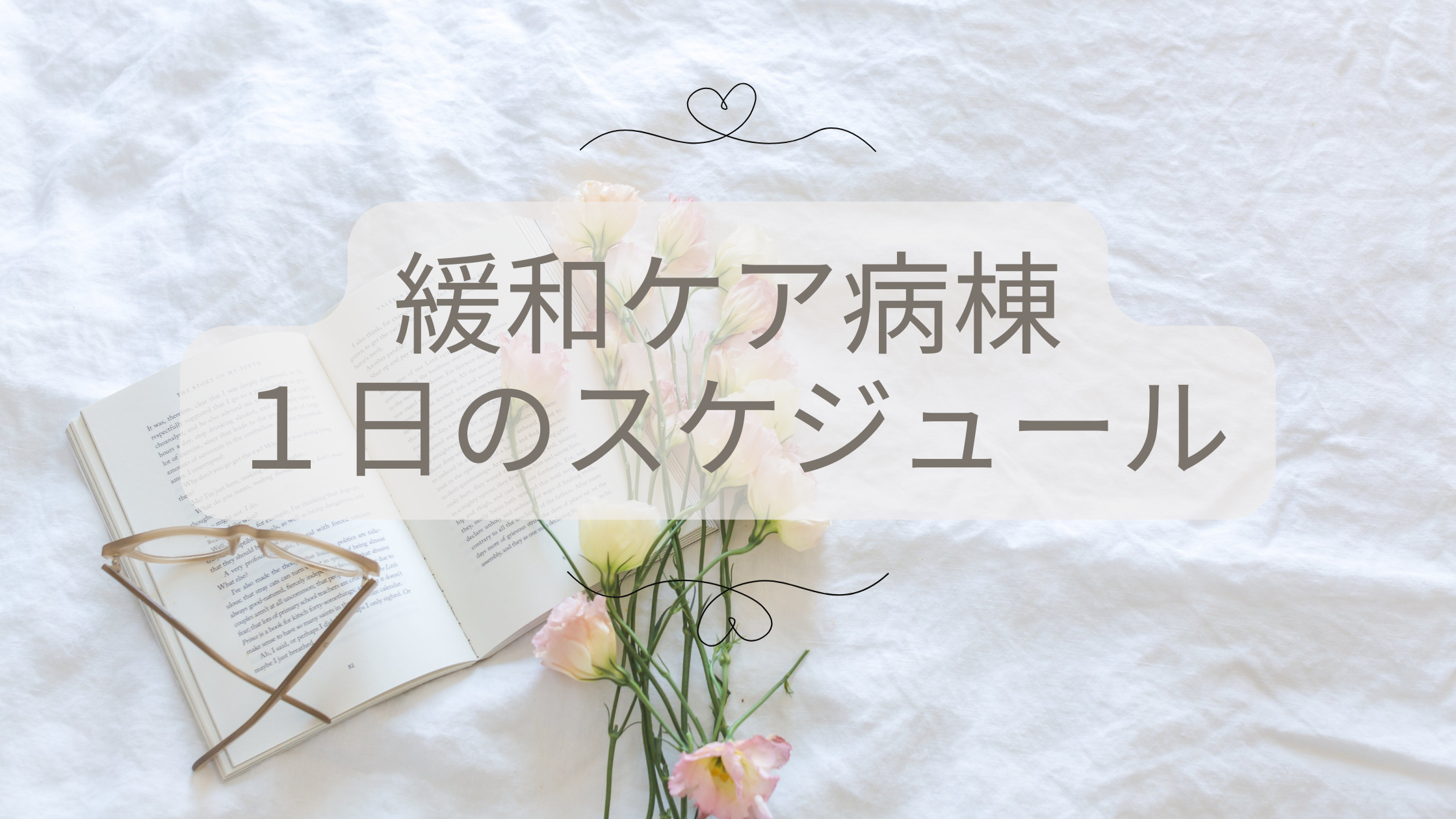
「将来は緩和ケア病棟で働くのもありかも…」
「緩和ケア病棟で実際にどんなことをしてるのか気になる」
「興味はあるけど、あまりイメージが湧かない…」
という方へ
ただ、実際に緩和ケア病棟で働いている人の素直な話が知りたいと思って調べても、そういった情報ってあまり出てこないですよね。
そこで今回は緩和ケア病棟で実際に働いてみてわかった、1日のスケジュールや業務内容について簡単に紹介していきます
病院によってもちろん差はあるでしょうが、緩和ケア病棟で働くことについてイメージできれば嬉しいです!
*この記事はこんな人におすすめ*
- 緩和ケア病棟で働くのに興味がある
- 緩和ケアで具体的に何をしているのか気になる
- 緩和ケア病棟に配属になったから事前に業務内容を知りたい
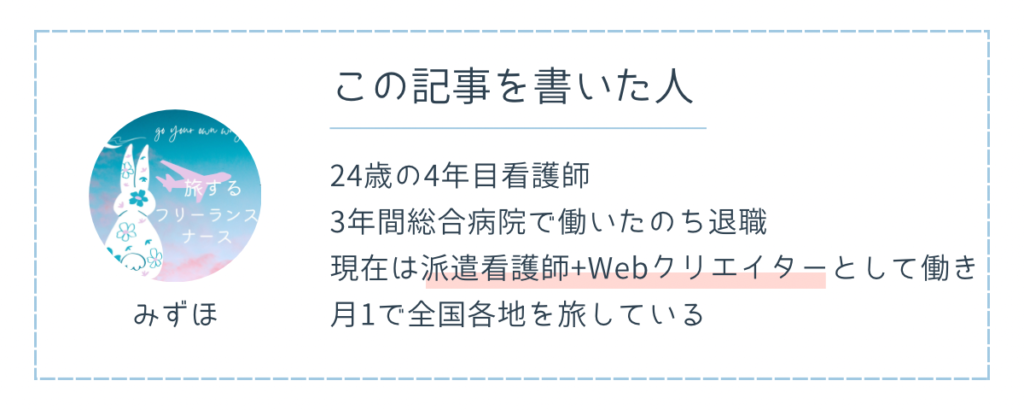

元緩和ケア病棟看護師です!
緩和ケア病棟 1日のスケジュール
まずは大まかな流れから ⇩

大まかな流れとしては以上の通りです。
基本的には情報収集、夜勤からの申し送り、午前中に時間処置や保清ケアを終わらせ、午後にICや患者さんとのお話・散歩などのリラクゼーション、という流れで毎日過ごしています。
これだけ見ると一般病棟との差って何だろう?ってなりますよね。
ここから、それぞれの項目で一般病棟との違いについて詳しく説明していきます。
緩和ケア病棟と一般病棟 業務内容の違い
バイタルサイン測定は最小限
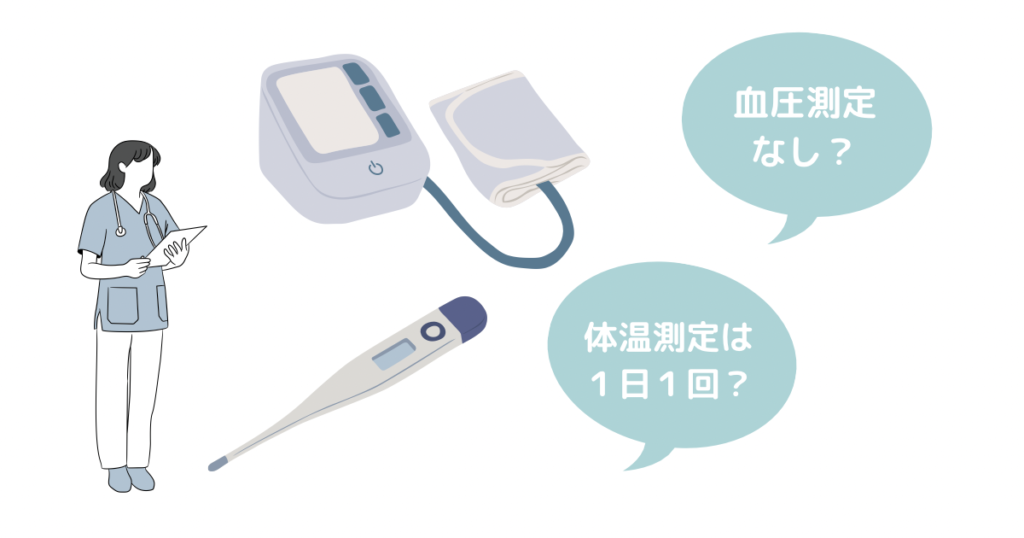
一般的な病棟などでは、朝・午前・午後・夜と1日4回バイタルサイン測定をする病院もあるかと思います。
これは手術や化学療法などの治療をしていると状態が変わりやすいことや、合併症や副作用を発見して早期治療・予防につなぐために必要性があることから行っていますよね。
緩和ケア病棟では基本血圧は測りません。体温やSpO2も1日1回の測定のみがほとんど。
これは終末期における状態変化は自然なものであることや、血圧測定自体が患者さんの苦痛につながるという考えからです。
看取りが近い方は橈骨動脈が触れるか、脈の触れ方で血圧の変化を察知しています。

終末期において大切な観察は
「患者さんに苦痛が生じていないか」を確かめるためのものですね
発熱で苦痛が生じていれば解熱剤やクーリングを検討する必要がありますが、
体温計で測らなくても患者さんに触れればアセスメントすることができます。
なので巡視の度に患者さんの様子をみて、聞いて、触れることで苦痛を察知し、それに伴う苦痛緩和のケアを行う
カルテに数字として記載しているのは1日1回ですが、巡視の度に触診で熱や脈を確認しています。
ケアの介助度が高く、処置が多い
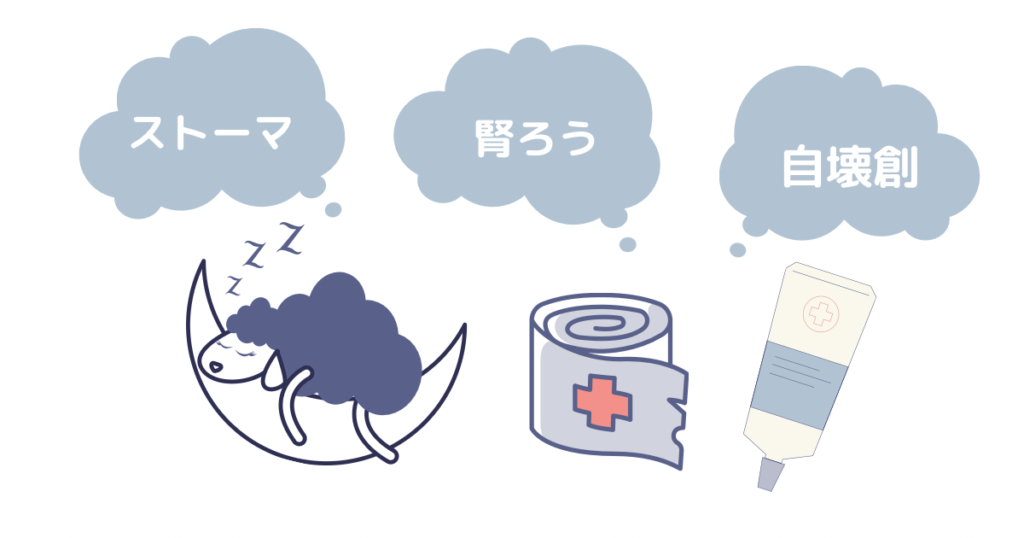
緩和ケア病棟に入院する=疼痛や呼吸困難感などの症状コントロールがうまくいかなかったり、ADLが低下してしまったり
”自宅で生活するのが難しい状態” で入院される方が多い
必然的に看護師が行うべき生活援助は多くなります。

廊下に歩いている患者さんがいると驚くレベル
加えて、今まで手術や化学療法など治療を行ってきた患者さんが多いことから
- ストーマ
- 経管栄養
- 腎ろう
- 抗がん剤による皮膚障害
- 自壊創
- 褥瘡
などの処置が多くなります。
逆に点滴や採血は激減。数ヶ月に1回あるかないか

正直、末梢留置のスキルは激落ちくん…
ただ緩和ケア病棟に来てから初めて行うという処置も多く、他のスキルや経験は増えます
麻薬の使用、管理が多い

終末期の患者さんは症状コントロールのため、ほとんどの方が医療用麻薬を使用しています。
内服でオキシコドン、オキノーム…
貼付薬でフェントステープ…
持続皮下注射でプレぺノン、アンペック…
とにかく麻薬の管理数が桁違い
厳密に管理しないといけないので、看護師間でのWチェックに意外と時間がとられます。

麻薬関連でインシデントが起きることもしばしば…
綿密なカンファレンス、ICが多い

緩和ケア病棟として「患者さん、家族がどのような最期を迎えたいか」を聞き
最大限それを叶えられるような支援が大事になります。
療養場所や会いたい人、医療者の介入の仕方やケアの方法まで
人によって価値観が本当に異なるので、ここをしっかりヒアリングして医療者で共有することが重要になります。

毎日のカンファレンスだけで1時間弱くらい話し合うこともざらにあります
加えて病棟内でのカンファレンスはもちろん、在宅連携とのカンファレンスも重要です。
終末期の患者さんは症状のコントロールがある程度つけられたとしても、治療をしているわけじゃないのでADLが劇的に回復することはありません。
なので、ご自宅での療養を希望された場合は訪問診療や訪問看護などとの連携が必須になります。
ここでも患者さんや家族がどういった考えを持っているのか、何を望んでいるのかを細かいところまでしっかり伝えていく必要があります。
そして家族へのICも重視していきます。
家族と医療者の間には「病状に対する認識の差」が生じているため、ここをなるべくすり合わせていく必要があります。
- 終末期は週単位、日単位で病状が変わることも多い
- 家族は病院にいる =元気になると思っていることが多い
などの理由で差が生じやすいというのを医療者がしっかり理解した上で、状態が変わるごとにタイムリーにICを重ねていきます。
家族がどのように考えているのか、認識についてしっかり聞き取るのが看護師の重要な役割です。

ここの認識の差が、家族からのクレームにつながることも多く…
緊張する場面の1つでもあります。
コミュニケーション、ケアに時間を多く使える

根治的な治療を行わないことから、点滴・検査出し・手術出し・入院処理など…
一般病棟で時間に追われる原因となっている業務が激減します。
その分患者さんとのコミュニケーションを大事にしたり、散歩やマッサージ、部分浴といった苦痛緩和のケアなどに時間を使います。
加えて上記で述べたカンファレンスや、家族とのコミュニケーションなどに時間を使います。

私自身、緩和ケア病棟に来てから「時間の流れがゆったりになったなあ」と感じます
もちろん緊急入院や、医療者も予想できていなかった状態の急変があったりしてバタバタする日もありますが…
それでも一般病棟時代の時間に追われすぎて
「看護って何だろうな」
と思っていた時と比べたら、患者さん一人ひとりに向き合って看護ができていると感じます。
まとめ
今回の記事では緩和ケア病棟の1日のスケジュール、業務内容についてまとめてみました。
- バイタルサイン測定は最小限
- 介助度が高い、処置が多い
- 麻薬の使用や管理が多い
- カンファレンスやICが多い
- 患者さんとのコミュニケーションやケアに時間を多く使える
緩和ケア病棟に興味のある人が、少しでも緩和で働くことのイメージができたら嬉しいです。

